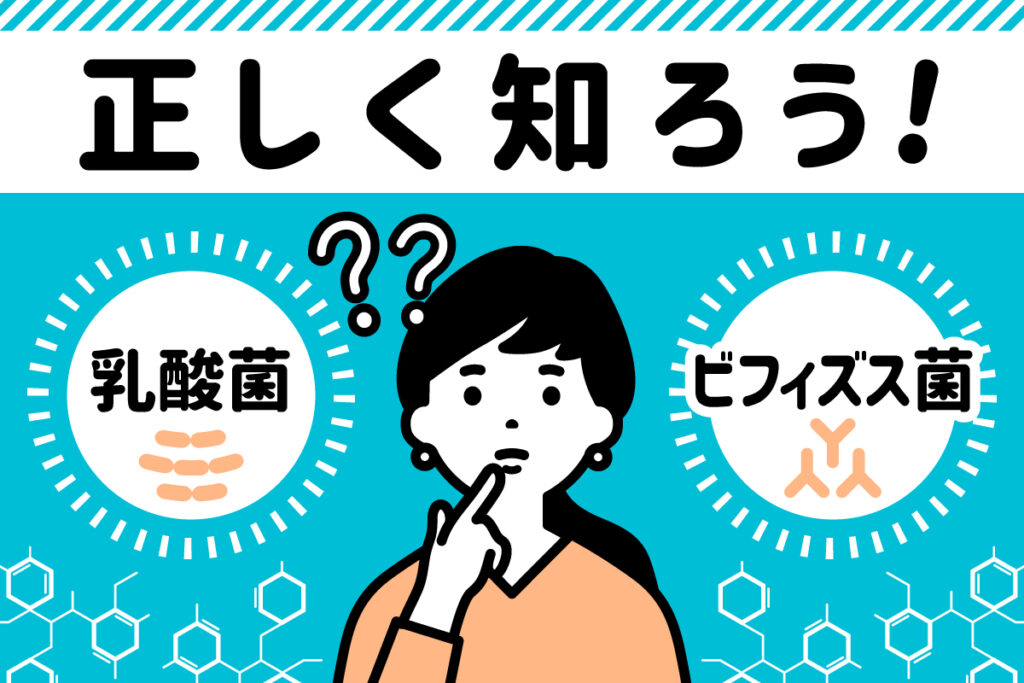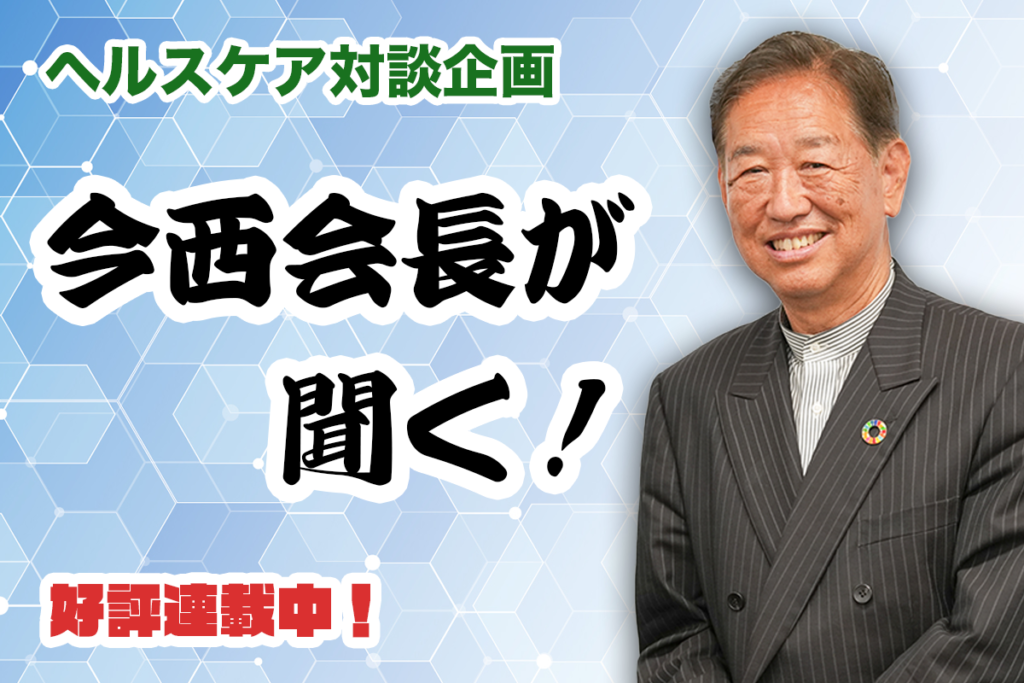新部会「ウェルネス交流・体験部会」発足
「ウェルネスがつなぐ ~人・まち・ミライ~」テーマに
体験型ヘルスケアを実践

公益財団法人日本ヘルスケア協会(JAHI)に新たな部会「ウェルネス交流・体験部会」が立ち上がり、7月22日(火)に第一回の部会活動がスタートした。近畿日本ツーリスト株式会社、ニプロ株式会社、スギホールディングス株式会社、スギメディカル株式会社、ナッジヘルステック株式会社の5社で部会は立ち上がり、交流と体験を通じたヘルスケアの樹立「ウェルネス」を目指すことを発表した。新部会は「ウェルネスがつなぐ ~人・まち・ミライ~」をテーマに掲げ、地域や店舗を旅行・スポーツといったイベントと絡ませ、持続可能な地域社会の構築へとつなげる。半年以内には第一弾イベントを開催する方針で、共にアクションを起こす部会員の参加も募った。(取材=中西陽治)
今西会長「前例のない〝実践型〟部会活動に期待」

JAHIの部会の活動は企業単体では実現しえない社会における行動変容を、部という組織で実践していく。
「ウェルネス交流・体験部会」設立に立ち会ったJAHIの今西信幸会長は「交流と体験を通じ、どのようなアクションが健康につながるか、を実践できる部会であってほしい」とコメント。
「そのためにはエビデンスとアクションの整合性を持たせる必要がある。ウェルネスのための〝交流・体験〟を掲げるのならば運動のエビデンスを実証してほしい。例えば日本は先進国でありながら、30年前まで『スポーツの時には水を飲むな』というのがまかり通ってきた。このようにスポーツは観念論で語られてきたため、なぜそれがウェルネスにつながっているのかの実証がない。交流と体験が人の健康と幸福につながるという部会のテーマは前例のないものとなるだろう。JAHIではこの大きなテーマを全面的にバックアップする。科学的なエビデンスに基づいて『体験・交流・スポーツをすればこれだけ健康によい』を証明してほしい」と期待を込めた。
髙川部会長「交流・体験×ヘルスケアでウェルネス実現の第一歩を踏み出す」
続いて「ウェルネス交流・体験部会」部会長の髙川雄二氏(近畿日本ツーリスト顧問)が部会活動に向けた思いを語った。
高川部会長は「『ウェルネス交流・体験部会』は治療・予防の枠を超え、人々の健康、社会との調和を通じた心の安寧を目指す。今、コミュニティや社会が抱える課題を乗り越えるだけでなく、個人において年齢性別を問わず興味を深めてもらい、体験と交流を生み出すことが重要だ。この部会活動が企業と地域が連携して持続可能な社会システムを創出することを確信している」と掲げた。

そして「今後、交流と体験によるウェルネスプログラムを実践していく。その上で、航空会社や公共交通機関、ホテルといった企業にも働きかけ部会員を増やしていきたい。部会活動は交流と体験そしてツーリズムでウェルネスを実現する第一歩となる、皆さんと共に成長していきたい」と抱負を語った。
近畿日本ツーリストは旅行会社として、東京オリンピックや世界陸上のサポートを行っている。これら大型スポーツイベントには日本国中で事前合宿が実施されており、同社は各自治体と組んで、スポーツを通じた交流・体験プログラムを組んでいる。今後増加するスポーツイベントに際し、事前合宿で地域の活性化、多様性ある地域を創り上げていく方針だという。
また、災害時のボランティアや交流を通じた復興活動にも注力しており、ツーリズムを通じて地域活性化と地域住民支援に貢献している。
スギ薬局グループ、ニプロ、ナッジヘルステックの強みを活かし
新しいサービスを創出する
キックオフとなる第一回の部会では、各部会員がウェルネス実現に向けたビジョンを語った。
スギホールディングスの主要子会社であるスギ薬局では、2024年10月からナッジヘルステックとニプロと協働し店頭での指先採血サービスを開始、現在では全国12店舗で展開している。部会活動を通じ、店頭における交流・体験イベントおよび薬剤師・登録販売者・管理栄養士・ビューティアドバイザーの職能を活かした活動を促進していく。
スギメディカルでは、オンライン診療や新たな医療体験といったサービスを進めており、部会活動を通じ地域医療に貢献する方針だ。

ニプロは医療機器、医薬品、診断薬などを病院や調剤薬局といった医療機関に供給しており、今後は地域や行政といったより大きな枠組みと取り組む必要があり、部会活動がそのフィールド拡大に貢献できると考えている。また医療を供給する立場として、拡大するフィールドに応じた新しいサービスや体験を生み出していく。
ニプロでは糖尿病関連の機器開発をしており、近年はシステム連携を進め、部会活動にも役立てていく考えだ。

ナッジヘルステックは、指先採血の健康測定サービスを提供しており、旅行会社やドラッグストア、医療機器を担う会社と連携し、エビデンスを構築していく。
副部会長の高川悟氏(ナッジヘルステック)は、部会立ち上げの理由について「健康管理や増進は一般の方にはハードルが高い。心理的なものも含めて、そのハードルを下げるきっかけを生みたい。部会活動を通じて、旅行体験や健康イベントなどで、健康管理や増進できるきっかけを提供していく〝新しいサービス〟を創り上げる」と骨子を語った。

「目的」「課題」「活動内容」から「具体的企画案」までを策定
ウェルネスとは「自分らしく、健やかに生きるためのライフスタイルの実践」であり、その実現のため、部会はスタートした。部会では早速「部会の目的」「ウェルネス実現に対する課題」「部会の達成内容」「成果物」「活動内容」がすり合わせされ、今後具体的な企画案を固めていくことを確認した。
部会の目的
・『ウェルネス』を提供し、ココロとカラダの健康を実践・促進
・個人の問題にとどめず、地域・企業・団体と連携して取り組みを推進
・科学的根拠と行動変容を軸に、持続可能なウェルネスサービスモデルの構築
なお高川副部会長は「社会的なつながりがウェルネスには欠かせない。心の安定や健康に興味をもっていただけるような形を構築していくべき」と補足した。
ウェルネス実現に対する課題
・体験価値の実感はあるが、数値的・科学的な裏付け(エビデンス)が不足
・実施効果を測るための手段・仕組みが未整備
・言葉だけが先行し、具体的な取り組みが不足
・ウェルネス=ハードルが高いという考え
部会の達成内容
・ウェルネス体験の可視化・定量化の仕組みを構築
・科学的根拠に基づいたプログラム設計と改善
・行動変容を促す体験設計と地域・組織の巻き込み
・ウェルネスを身近に、気軽にできる環境作り
成果物
・ウェルネス体験の効果を文献化・発表
・自治体や企業と連携した体験サービスの構築・提供
・社会実装や制度への提言へつなげる
活動内容
・ウェルネス体験プログラムの企画
・各地の取り組みをまとめたウェルネスアクティビティマップ作成
・効果測定・フィードバックサイクルの実装

今年度中にも第一弾イベントを開催予定
これら企画を積み上げつつ、ツーリズムやサービスと組み合わせていき、結果からエビデンスを構築し、学会発表にまで昇華させていく方針だ。「ウェルネス交流・体験部会」では目的、課題、活動内容など方針をまとめ、「ウェルネスがつなぐ ~人・まち・ミライ~」を部会活動のテーマに定めた。
部会活動の第一弾を都内の自治体に定め、各種検査や体験を通じたイベントを企画している。少なくとも半年以内には何らかのイベントを開催し、ウェルネスツーリズムや継続性・収益性ある健康イベントへと役立てていく。